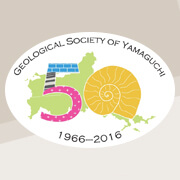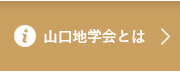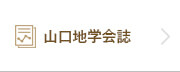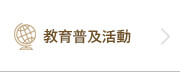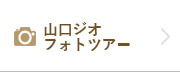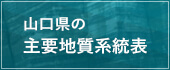山口地学会とは
会長挨拶

- 深田 佳作
大和田会長の後任として、2024(令和6)年12月の総会で会長に任命されました深田です。歴史と伝統ある山口地学会の継続と発展のために、精一杯務めて参ります。
当会は、地学の研究をとおして、山口県の自然科学及び文化の普及と発展に寄与するとともに会員相互の親睦を図る目的で昭和41年に設立されました。毎年実施している巡検活動や会誌発刊はもとより、「山口県の岩石図鑑」や「山口県地質図」等の出版物をとおして、山口県の地学教育、研究に貢献してきました。
一方、学校現場では地学教育の縮小が進み、若者の地学離れが顕在化するなか、記憶に新しいところでは、昨年元旦に石川県能登半島で発生した最大震度7の能登半島地震や8月に宮崎県で発生した最大震度6弱の地震とその後政府から発表された「南海トラフ地震臨時情報・巨大地震注意」などで、テレビや新聞等のマスメディアやインターネットを通して「活断層」や「直下型地震」、「プレート境界」などの地学に関する様々な用語が飛び交い、身近な防災減災の視点からも県民の関心を集めたところです。
また、近年、福井県を中心に全国各地で見つかる新種恐竜の発見や、宇宙に目を向ければ探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」の小惑星探査による太陽系誕生の究明など、地殻や火山、地震、地形地質から太古のいきもの、延いては宇宙の誕生まで、子どもから大人までが地学に対して様々な興味を抱き、そのニーズは年々高まっているように感じます。
当会は、大学の教官や小中高校の教諭、地質調査会社や設計コンサルタント会社の社員など日常から地学と深く係わる人をはじめ、大学生や地学に強い興味を持つ研究者など、地学に高い見識を有する幅広い人材が集まった県内で唯一無二の団体です。
これまでの研究等で得られた様々な知見や技能を活かし、高まりつつある県民の地学へのシーズ、ニーズに少しでも応えるため、標本観察会など理解醸成に係る教育普及活動を、会員の皆様と話し合いながら積極的に展開していきたいと考えています。
こうした活動をとおして、新たな会員確保や育成、会員相互の連携に努めて参りますので、どうかお力添えよろしくお願いいたします。
2025(令和7)年1月